新訳 「茶の本」 第一章:茶に広がる人間性(3/4)
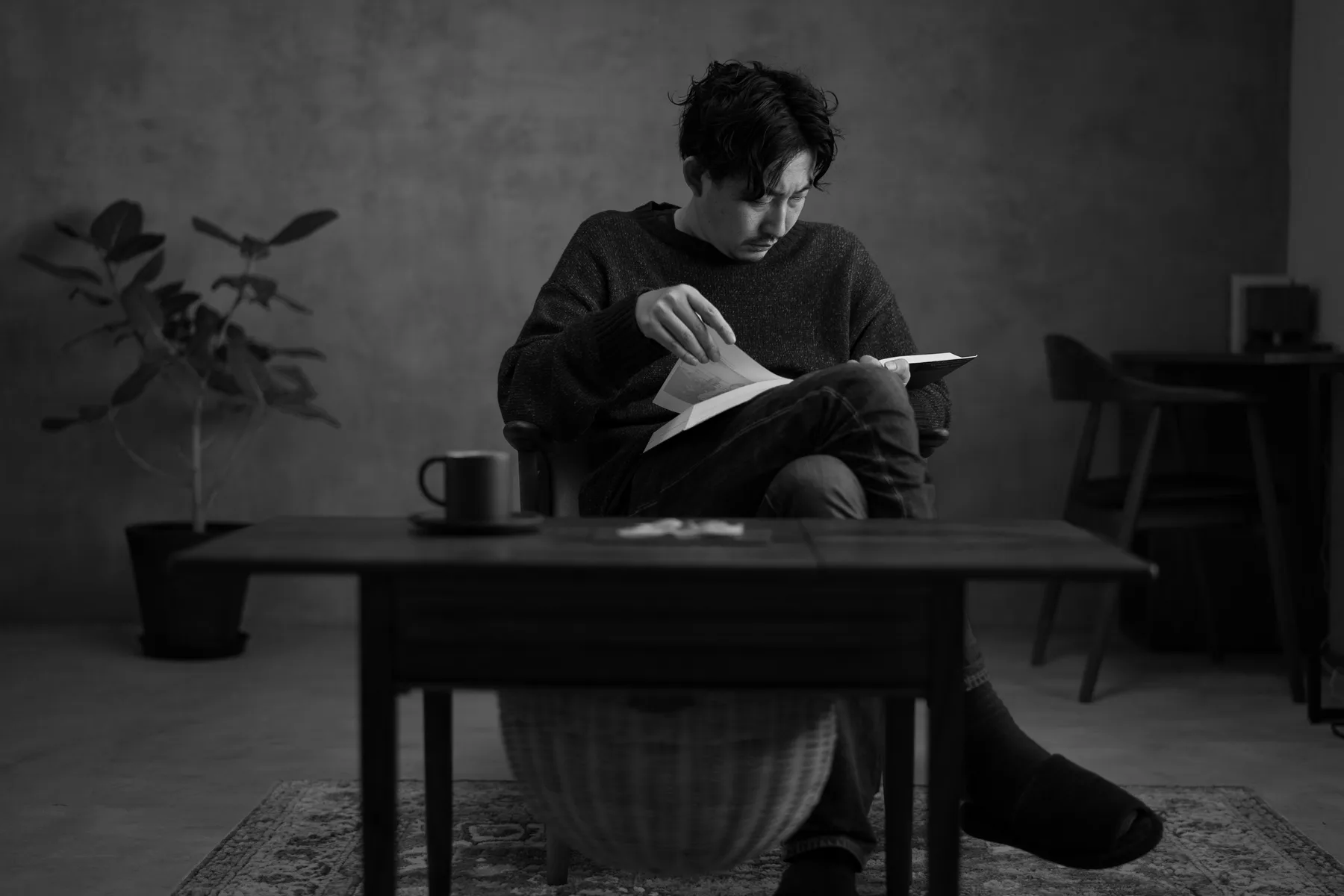
by 高崎健司
< 前回からの続きです。
第一章.茶に広がる人間性 (3/4)
一杯の茶の中で、西洋と東洋は出会ってきた。
それは、アジアの儀式で唯一世界から尊敬を集めるものである。
白人は東洋の宗教やモラルについては嘲笑してきた一方で、この褐色の飲み物だけはためらいなく認めたのだ。
午後の紅茶は西洋社会でも重要な機能を担っている。
「カチャカチャ」とお盆やソーサーの繊細な音がなり、「さらさら」と服が擦れる音が、柔らかなおもてなしの心を感じさせる。
クリームと砂糖はいりますか?というお決まりのやりとりの中に、茶への尊敬が確立していることをわれわれは感じるのである。
茶会に招かれた客は自分を手放して、どんなお茶がでてくるのかを相手に委ねるのであり、そこにこそ東洋の精神が現れているのだ。
茶に関するヨーロッパ最古の文献は、あるアラビア人の旅行記に見出され、それによると879年以降の広東における主要な税収は塩と茶によるものだったという。
マルコポーロは、1285年に茶税を独断で引き上げたことにより、中国の大臣が罷免されたことを記している。
大航海時代に入り、西洋はより東洋を深く知り始める。
16世紀の終わり、オランダ人によって東では茂みの低い木から心地の良い飲み物が作られていると伝えられた。
ジョヴァンニ・バティスタ・ラムージオ(1559年)、L・アルメイダ(1576年)、マッフェーノ(1588年)、タレイラ(1610年)といった旅人も茶を伝えた。
その1610年、オランダ東インド会社の船が初めて茶をヨーロッパにもたらした。
フランスでは1636年に知られるようになり、1638年にはロシアに伝わった。
1650年に、イングランドは茶を歓迎し「医師によって認められた中国の飲み物、中国人にチャと呼ばれ、他の国ではティーと呼ばれるもの」と述べたのである。
良いものでも新しいものは、新しいという理由だけで抵抗にあうのが世の常だが、茶も例外ではなかった。
ヘンリー・サヴィル(1678年)のような反対派は、茶を飲むことを汚らわしい習慣として糾弾し、ジョナス・ハンウェイは、『茶論』1756年で、茶を飲むと男性は力強さと凛々しさを失い、女性は美しさを失うように見えると述べた。
そのはじまりにおける値段の高さ(1ポンドあたり約15〜16シリング、現代の価値で数万円)は、茶を庶民からほど遠い「貴族が王族に贈る接待のための高級品」にした。
しかし、そこから庶民の間でも喫茶という習慣は急激に広まっていくのである。
18世紀前半、ロンドンのコーヒーハウスは、実質的にお茶を楽しむ場となり、アディソンやスティールのような文化人たちが『一杯の茶』を楽しみながら社交する場所となった。
この飲み物はすぐに生活にとって欠かせないものとなり——課税の対象ともなった。
近代史において、茶はそれほどまでに重要な役割を果たしてきたのだ。
植民地であったアメリカは、茶に対する重税に耐えきれなくなるまで、イギリスの支配を甘じて受け入れてきた。
アメリカの独立戦争は、ボストン港に停泊していたイギリスの船から愛国者グループが茶を海に投げ捨てたボストン茶会事件に端を発するのである。





