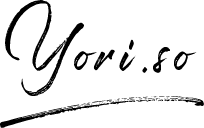エミリー・ディキンソン「石ころって いいな」

by 小谷ふみ
この連載は、世界の名詩を現代にあわせた新訳でお届けするボイスレターです。

こんにちは。
本格的な春の目覚めに向け、今日は、髪を短く切り揃えました。帰り道、すれ違った学生さんのコートの下、胸元にちらり、ひと足早く咲いた春の花を見つけました。卒業、門出の季節を迎えているのですね。おかわりありませんか。
学生のころは、進級や進学といった節目がありましたが、大人になってからの日々には区切りがつきづらいものです。ですが、特に人生のイベントがなくても、この時期は自然と気持ちが改まりますね。
この春、赤ちゃんの頃から見てきた近所の子どもたちが、小学校にあがります。
我が家の外壁には、少し低いコンクリートの台のような場所があり、そこがよく外遊びをする彼らに重宝されています。ちょうど幼児の腰の高さなので、彼らの遊びのおもむくまま、ベンチやジャンプ台になったり、時に歌や踊りのステージになったり、そして、おままごとのキッチンになったりします。
キッチン利用時には、どこからともなく登場する「パンケーキの石」と呼ばれる、丸くて平たい石があります。大人の手のひらほどのサイズの、色白のきれいな石です。灰色のコンクリートのキッチンの上で、木の実や葉っぱでデコレーションされると、赤や緑の彩りに映え、つい頬張ってみたくなるほど美味しそうなのです。
パンケーキの石は、私たち近所の大人たちとともに、子どもたちがあれこれ工夫しながら、出来るようになってきたことの数々を見守ってきました。
ところが、春一番が吹いたころのことです。パンケーキの石が、半分に割れてしまっていたのです。丸いパンをちょうど真ん中でちぎったような片割れが、ある日、ころんと転がっていました。子どもたちは一瞬、戸惑っていましたが、手に馴染むチョークにして、すぐ新しい遊びの仲間として受け入れていました。でも、もう半分が、どこを探しても見当たらないのです。
大人の私の方が喪失感に苛まれ、片方がいなくなって初めて「パンケーキの石」のこれまでの歩みに、思いを巡らしました。そもそも、海岸の砂が長い時間をかけて固まってできたような石が、どこから、どうやって、丘の上のコンクリートキッチンにたどり着いたのだろう、と。
石ころは、地球の子ども。
ある時、ふるさとから飛び出して、ごろごろ転がり、他の石とぶつかりながら、だんだんと角が取れ、丸くなり、やがて、子どもの手のなか、やさしい形に。そして、また途方もない時間をかけて、ふるさとへ還ってゆきます。
じっと見つめていると、私たちの時計では計れないほどゆっくりと呼吸をしている、ひとつの「意志」を持った生きもののようにも思えてきます。石だけに。
この春、子どもたちが自分の足で小学校に通えるまでに成長したのを見届け、「あとは頼んだよ」と二手に分かれ、春風に誘われるまま、旅の続きに出たのかもしれません。いつかまた、別々の物語を携え、ひとつになることを夢見て。
どこにでもある丸い石ころ。でも、小さな隣人たちの人生の中で、あっという間に過ぎてしまう幼児期を、ともに過ごした特別な石であったことにはかわりはありません。
新年度、パンケーキの石も、次のステージへ。
きっとどこかでまた別の名前を付けられたりしながら、
「寄り道だって、自分の歩む道」と気ままに転がり続けている。
そんな「石ころの生きざま」に憧れてしまう詩をおくります。
How happy is the little Stone
That rambles in the Road alone,
And doesn't care about Careers
And Exigencies never fears ‒
Whose Coat of elemental Brown
A passing Universe put on,
And independent as the Sun
Associates or glows alone,
Fulfilling absolute Decree
In casual simplicity ‒石ころって いいな
道ばたに ひとり ころころと
うまく歩もうなど 思わずに
危ないことも 怖がらず
その飾らない茶色の衣は
過ぎゆく宇宙がくれたもの
おひさまのように 我が道をゆきながら
誰かと力を合わせたり ひとり磨かれ光ったり
自らの命(めい)を果たし 尽くそうと
自由気ままな 無邪気さで
20代のいつかの春、新卒で入社した会社を辞める時、もうすぐ定年退職のマネージャーに挨拶に行った時のことです。3年も経たずに辞めることを、不甲斐なく、恥ずかしく思う、そう漏らすと、
「『石の上にも3年』ならば、あなたは、私の歳になるまでに、あといくつ石の上に座れる?まだ随分あるでしょう」と。
帰り道、図々しくも100歳まで生きるとして、残りの人生を3で割ってみました。すると「あと最大25個も座れるではないか」と、気持ちが少し楽になったのでした。
以来、先の人生を3で割る癖もついてしまいました。確かに、3の倍数だけは順調に重ねたものの、座っては転がり落ちを繰り返し、座れた石はごくわずか。気づけば、手持ちの石も意外と少なくなってきていることに、ちょっと慌てる時もあります。
憧れは、パンケーキの石。
この場に留まり、ひとつのことに心と時間を費やし極める「苔むす石」であり、
まだ見ぬ世界へと、軽やかに身を投じてゆく「転がる石」でもありたい……。
そんなハイブリットな石を心に。
あなたも、どうぞ、石の意志のままに。
じっくり、取り組みたいことがある。
まだまだ、見てみたい景色もある。
あなたの町に吹く春風が、
どちらに向かう背中も、やさしく撫でてくれますように。
風の行方を楽しみに、また手紙を書きます。
あなたのいない夕暮れに。
文:小谷ふみ
朗読:天野さえか
絵:黒坂麻衣
小谷ふみコメント:エミリー・ディキンソンの私訳によせて
最近、友人と絵はがきのやりとりしているのですが、彼女が選んだ絵はがきとカラフルな文字から、その暮らしぶりや家族のようす、さらには彼女の内側に広がる世界そのものまでもが、切手が貼られた小さな窓から伝わってくるようです。
「手紙は、肉体は伴わず、精神だけを伝えるという点で、私にはいつも不滅そのもののように思われるのです」という言葉を残したアメリカの詩人 エミリー・ディキンソンは、今から150年ほど前、南北戦争の時代に生き、生前は無名でしたが、1700編もの詩を残していました。
その暮らしは、いつも白いドレスを身にまとい、自宅からほとんど外に出ることはありませんでした。そして社会と世界と、彼女なりの距離を取りながら、詩をひそやかに書き続け、限られた人と手紙のやりとりをして過ごしました。
彼女の詩や手紙には、閉じた窓の向こうに彼女が見つけた、いつまでも失われることのない世界が広がっています。“stay home” ”keep distance” この閉ざされた日々に、彼女の「詩」という窓の向こうを、一緒に眺めてみませんか。
2020年 秋 小谷ふみ

小谷ふみ
書く人。詩・エッセイ・物語未満。
うろうろと、おろおろと、揺らぎながら揺らがない言葉を紡ぎます。
夫と息子とヤドカリと、丘の上で小さく暮らしています。いまやりたいことは、祖父の一眼レフを使いこなす、祖母の着物を着こなす(近所のスーパーに着て行くのが億劫でなく、そして浮かない)こと。
本「よりそうつきひ」(yori.so publishing)・「やがて森になる」・翻訳作品集「月の光」(クルミド出版)・詩集「あなたが小箱をあけるとき」(私家版)など。