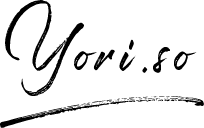エミリー・ディキンソン「草原をつくるなら クローバーとミツバチを」

by 小谷ふみ
この連載は、世界の名詩を現代にあわせた新訳でお届けするボイスレターです。

こんにちは。
日を追うごと、草木がぐんぐん育ち、うす緑色だった柔らかな葉っぱも、その濃さと力強さを増しています。見ているだけで、元気を分けてもらえそうですね。おかわりありませんか。
命の息吹を、そこかしこに感じる5月、私はいくつかの記念日を迎えます。
毎年、この時期になると、春の大掃除をしながら、棚の奥のホコリっぽくなった思い出ボックスを取り出します。そして、1年ぶりの思い出と再会し、また新たに、この1年に得た記憶を箱につめます。
今年は、さらに手を伸ばし、棚のもっと奥に眠る、ボロボロの箱を開いてみました。
そこには、学生時代の寄せ書きや、友達にもらった特別なお土産などが入っています。それは、沖縄の星の砂の入った小瓶、デンマークの街並みのスノードーム、アフリカの動物のキーホルダーなど、時代も、国も、さまざま。私のものではない、旅の思い出。
私には、難しい病が眠っているので、大きな旅に出ることは叶いません。でも、沖縄の海がテレビに映れば、星の砂の感触が、本の舞台がデンマークの街ならば、スノードームに舞う雪が……遠い昔、そこにいたことがあるかのように、わずかな懐かしさが、胸に広がります。
旅のかけらを集めた箱の中は、小さくても、私の世界そのものなのです。
箱の奥をさらに掘り進めると、小さな金の大仏が10体、発掘されました。
一瞬ギョッとしましたが、これらは、小学校の社会科見学の鎌倉で、自分が買ったものです。5センチほどの大きさながら、精巧にできたお姿に心惹かれ、自分と家族、塾の友達のお土産にと選んだのでした。
でも、渡すタイミングを逃すこと、四半世紀以上。箱のフタを開くたび、ギョッとして、「このチョイスは……」と、過去の自分への言葉を飲み込みます。
そして、心の中で、「ありがたく、ここまで歳を重ねております」と手を合わせ、秘密の仏殿の扉を、ふたたび閉じるのでした。
他にも、もう会えない彼女がくれた、オレンジ色の花束のリボン、涙も笑いも共にしてきたのに、1つだけ欠けてしまったお揃いのマグカップ。どれも、誰かにとっては、ガラクタのようなもの。でもそれが、自分にとっては、思い出のものであったり、どうしても捨てられないもの、また、特別な思い入れがあるものなのです。
「これは世界のかけら」また「これは思い出のしっぽ」と言って、ガラクタは増えてゆく一方。でも、いつか、ある時、たったひとつを残し、すべてを手放そうと思っています。
さいごのさいごに、手にしていたいものは、何だろう。
自分に問いながら、その「たったひとつ」とは、まだ出会えていないような、すでに持っているような。それが分かるまで、今しばらくは、小さなガラクタを集めてしまいそうです。
果てのない想像の世界へと、
はたまた、底のない深き思い出へと、
連れ出してくれるのは、いつも「小さきもの」。
今日は、そんな、
小さなひとつから広がる世界の詩をおくります。
To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do, If bees are few.草原をつくるなら クローバーとミツバチを
クローバーひとつ ミツバチ1匹
それから 思い描くこと
ミツバチが いないなら
思い描く それだけで
うちの庭のクローバーも、タテに、ヨコに、もこもこと、成長しています。
この緑の一角を、じっと見つめていると、草原にいるような気持ちになります。花が咲けば、ちょうちょも、ハチも、やってくるメルヘンな風景。
「クローバー畑に寝そべって、空を眺める」という、憧れのシチュエーションを再現してみたところ、背中がびしょびしょ、虫だらけになりました。
クローバーは、かわいい様子からは想像できないほど、根っこが強く、結びつきあい、水分をたっぷり抱いて、小さな生きものを、育んでいるのです。
現実はいつも、想像の、少し斜め上をいくものだと、びしょびしょの背中に実感しました。
世の中のすべてを、ひとりで経験することはできませんが、
沖縄の星の砂、デンマークの雪、そして、大仏10体のゆくえ……
想像のフレームの外は、上下左右、ちょっと斜め、全方位に広がっています。
そんな箱の中の無限の可能性を、ぼんやり見つめながら、今年も5月を迎えています。
どこかで、生まれたばかりの赤ちゃんが、泣いています。
泣き声のさきに、広がる未来が、
豊かなおどろきに満ちた、すこやかな日々でありますように。
そして、今は小さなその手に、
いつか、たったひとつの、ガラクタを。
また手紙を書きます。
あなたのいない夕暮れに。
文:小谷ふみ
朗読:天野さえか
絵:黒坂麻衣
小谷ふみコメント:エミリー・ディキンソンの私訳によせて
最近、友人と絵はがきのやりとりしているのですが、彼女が選んだ絵はがきとカラフルな文字から、その暮らしぶりや家族のようす、さらには彼女の内側に広がる世界そのものまでもが、切手が貼られた小さな窓から伝わってくるようです。
「手紙は、肉体は伴わず、精神だけを伝えるという点で、私にはいつも不滅そのもののように思われるのです」という言葉を残したアメリカの詩人 エミリー・ディキンソンは、今から150年ほど前、南北戦争の時代に生き、生前は無名でしたが、1700編もの詩を残していました。
その暮らしは、いつも白いドレスを身にまとい、自宅からほとんど外に出ることはありませんでした。そして社会と世界と、彼女なりの距離を取りながら、詩をひそやかに書き続け、限られた人と手紙のやりとりをして過ごしました。
彼女の詩や手紙には、閉じた窓の向こうに彼女が見つけた、いつまでも失われることのない世界が広がっています。“stay home” ”keep distance” この閉ざされた日々に、彼女の「詩」という窓の向こうを、一緒に眺めてみませんか。
2020年 秋 小谷ふみ

小谷ふみ
書く人。詩・エッセイ・物語未満。
うろうろと、おろおろと、揺らぎながら揺らがない言葉を紡ぎます。
夫と息子とヤドカリと、丘の上で小さく暮らしています。いまやりたいことは、祖父の一眼レフを使いこなす、祖母の着物を着こなす(近所のスーパーに着て行くのが億劫でなく、そして浮かない)こと。
本「よりそうつきひ」(yori.so publishing)・「やがて森になる」・翻訳作品集「月の光」(クルミド出版)・詩集「あなたが小箱をあけるとき」(私家版)など。